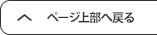冷蔵庫の温度って何度?食品ごとの保存先と鮮度長持ち&節電法

冷蔵庫って「野菜室」や「チルド室」「パーシャル室」、いろいろなスペースがあるけど、どこに何を入れればいいの?各部屋の温度やそれに適した食材を知っておくと、冷蔵庫をより便利に使え、食品の鮮度を長持ちさせられます。
この記事では、冷蔵庫の部屋ごとの具体的な温度の解説をはじめ、どんな食品を入れればいいのかについて詳しく解説しています。また、冷蔵庫の適正温度を保つコツも紹介しているので、「食品の鮮度をキープしたい」「なるべく省エネで使いたい」という方は、ぜひご参考にしてみてください。
冷蔵庫のスペースごとの温度と適した食材

家庭用の冷蔵庫には、「冷蔵室」「野菜室」「チルド室」「パーシャル室」「冷凍室」など、いくつかのスペースがあり、それぞれ保存する食品に適した温度が設定されています。どこにどんな食材を入れればいいのかを知って、食品の鮮度を長持ちさせ、よりおいしく保存できるようにしましょう。
| 冷蔵室 | 野菜室 | チルド室 | パーシャル室 | 冷凍室 |
|---|---|---|---|---|
| 約2〜6℃ | 約3〜8℃ | 約0℃ | 約-3℃ | -18℃以下 |
冷蔵室
冷蔵庫の一番上にある一番広い部屋、それが冷蔵室です。冷蔵室の温度は約2〜6℃。特に日常でよく使う卵や豆腐、ヨーグルト、ジュースなどの要冷蔵品を入れることが多いでしょう。また一般的に、味噌や醤油、マヨネーズやケチャップなどの調味料は、開封した後は冷蔵室で保存することを推奨されています。
野菜室
野菜室の温度は約3〜8℃と、冷蔵室に比べてやや高め。また、湿度も維持できるように作られているので、野菜や果物などの乾燥を防いでフレッシュなまま保存できます。
ただし、じゃがいもや里芋などのイモ類、玉ねぎやごぼうなどの根菜類は常温で保存すると鮮度が長持ちしやすくなります。野菜の種類にも目を向けて、最適な保存場所を見極めてみましょう。
チルド室
チルド室の適正温度は、約0℃が目安です。冷蔵室よりも低温で保存でき、食材が凍る寸前の状態を保てるため、より長く鮮度を維持キープすることができます。
優先的にチルド室に入れたいのが、特に鮮度が落ちやすい、肉や魚介類などの生鮮食品です。また、ハムやベーコン、ちくわなどの加工食品も、冷蔵室で保存するよりも風味を保ちやすくなります。また、発酵食品は温度が低いと発酵のスピードがゆっくりになるため、納豆やチーズなどのおいしさをより長くキープするには、チルド室で保存するのがおすすめです。
パーシャル室
パーシャル室の温度は、食材が微妙に凍結した状態をキープできる約-3℃。チルド室よりもさらに鮮度を保ちやすいほか、完全に凍らせてしまうわけではないので、解凍の手間をかけずすぐに食材を調理できることが大きなメリットです。
特にその真価を発揮しやすいのが、肉や魚介類などの生鮮食品。わずかに凍らせることでさらに鮮度が長持ちしやすくなり、解凍の手間もいらないので、すぐに調理に使えます。
いつもの食材をもっとおいしく保存して、料理にも便利に使いたいという方は、ぜひパーシャル室の搭載された冷蔵庫をチェックしてみて下さい。
冷凍室
冷凍室の温度は、-18℃以下になるよう設定されています。-18℃以下の環境では微生物の活動がほとんど止まるため、食材を長期間安全に保存することができます。アイスクリームや冷凍食品はもちろん、肉や魚介類、パンやごはんなどを長期保存したいときに活躍するでしょう。料理を一度にまとめて作り置きしたい方、生鮮食品をまとめ買いしたい方は、なるべく冷凍室のサイズが大きな機種を選ぶのがおすすめです。
なお以下の記事では、冷凍庫の適正温度や、温度が高くなる時の対処法について詳しく解説しています。気になる方は、ぜひこちらもご参考にしてみて下さい。

-
冷凍庫の適正温度は?温度が高くなる原因や対処方法を解説!
- 家庭用の冷凍庫の温度は、JIS規格(日本産業規格)によって-18度以下と定められています。冷凍庫の温度が-18℃を上回ってしまうときに考えられる原因やその対処法、温度を適正に保つコツなどを解説します。
- 詳しく見る
冷蔵庫の設定温度はどんなときに変えればいい?
機種によっても異なりますが、一般的な冷蔵庫は「弱」「中」「強」のように、おおまかに設定温度を変えることができます。では一体どんな時に設定を変えればいいのかというと、お部屋の温度が極端に高い、もしくは低いときです。たとえば、真夏でエアコンをつけない期間が長く、室温が高すぎて冷蔵庫が冷えにくくなってしまう場合は、温度を「強」に設定したほうがよいでしょう。また、冬場で室温がかなり下がる環境であれば、設定を「弱」に変えることで余計な電気代がかかることを防ぐ効果が期待できます。
一方で、夏場と冬場はエアコンがついていて室温が一定にキープされている場合、設定温度は初期設定の「中」のままで問題ありません。この状態で設定温度を変えてしまうと、冷蔵庫が冷えにくくなったり冷やしすぎたりして、余計な電気代がかかってしまうこともあるので注意が必要です。
- ※冷蔵庫の構造や温度の設定方法は、メーカーや機種によって異なります。具体的な操作方法は、お使いの冷蔵庫の取扱説明書を参照してください。
冷蔵庫の温度を上手に管理して省エネにつなげよう

冷蔵庫は冷気を密閉して一定の温度にキープしていますが、ドアを頻繁に開けすぎたり熱いものをそのまま入れたりすると、適正な温度が保てなくなることもあります。すると庫内が冷えにくくなり、余計な電気代がかかってしまうこともあるので、注意が必要です。
冷蔵庫を上手に使いこなすには、日ごろからちょっとした工夫を心がけることが大切。ここでは、冷蔵庫を適正な温度に安定させるために気をつけたい5つのコツをご紹介します。
1.ドアを開ける回数は少なめに
ドアを開けたときに入り込む暖かい空気は、冷蔵庫の温度を上げる一番の原因です。なるべくドアを開ける回数を減らして、余計な電気代がかからないように注意しましょう。また、よく使うものは前のほうに置くなど普段から冷蔵庫の中身を整理し、冷蔵庫を開けている時間をなるべく短くすることも、電気代を節約することにつながります。
2.温かいものは冷ましてから入れる
出来立ての料理をそのまま冷蔵庫に入れてしまうと、食品の熱で庫内の温度が上がり、冷却能力が落ちるだけでなく余計な電気代もかかってしまいます。料理を冷蔵庫で保存したい場合は、いったん粗熱を取り常温まで冷ましてから庫内に入れるようにしましょう。
3.冷気の吹き出し口をふさがない
冷蔵庫は吹き出し口から冷気を送り出し、庫内に循環させることで食品を冷やしています。食品を詰め込みすぎて吹き出し口がふさがってしまうと、冷気が行き渡らなくなり、冷蔵庫が冷えにくくなってしまうこともあるので注意が必要です。
吹き出し口の場所は機種によっても異なりますが、一般的には上の棚の奥のほうにあり、知らぬ間に古い食品が溜まってしまいがち。なるべく吹き出し口の周辺はスペースを開けながら使うようにするとよいでしょう。
4.食材を詰め込みすぎない
冷蔵庫は庫内に冷気を循環させることで、食品を冷やしています。そのため、あまりに詰め込みすぎると空気の流れが悪くなり、冷蔵庫が冷えにくくなってしまうこともあるので注意が必要です。庫内にはパンパンになるまで詰め込みすぎないようにすると、冷却効率が上がって余計な電気代がかかることも防いでくれます。
なお、冷凍室は凍った食材自体が保冷材の役割を果たすため、隙間なくぎっしり詰め込むことで冷却効果が高まりやすくなります。スペースごとに収納方法を工夫すると、より上手に冷蔵庫を使いこなすことができるでしょう。
5.冷蔵庫の周辺に放熱スペースを確保する
冷蔵庫は庫内を冷却する際、背面や側面から熱を逃がしています。そのため、本体を壁にぴったりくっつけて設置していると、放熱がうまくできず冷蔵庫が冷えにくくなり余計な電気代もかかってしまいます。
冷蔵庫を正しく設置するには、本体の周りにある程度すきまを空けること。具体的な目安は取扱説明書に記載されているので、十分なスペースが確保されているかをチェックしてみましょう。
古い冷蔵庫の温度が上がる場合は買い替えもおすすめ

もし長年使った冷蔵庫の使い方を工夫しても冷えが悪い場合は、本体の寿命が近づいているサインかもしれません。一概には言えませんが、冷蔵庫の寿命の目安は一般的に約10年とされていて「消費動向調査 2025年3月 内閣府調べ」によると冷蔵庫の平均買い替え年数は13年という調査結果が出ています。冷蔵庫が完全に故障してからの買い替えになると、中身の食材の扱いに困ったり冷蔵庫が使えない期間が出てきたりするため、まだ動いているうちに買い替えの検討をするのがおすすめです。
特に、長年使った冷蔵庫に「冷えにくくなった」「異音がする」「水漏れがある」などの症状が出ている場合は、そろそろ買い替えのタイミングが近づいていると判断してよいでしょう。修理という選択肢もありますが、長年使った冷蔵庫は修理してもまたすぐに別の個所が壊れてしまったり、メーカーの部品保有期間(冷蔵庫の場合は9年)を過ぎていてそもそも修理自体ができなかったりすることもあるので注意が必要です。
また、最近の冷蔵庫は昔のモデルに比べて省エネ性能が進化しているため、買い替えるだけで電気代の節約になることも多いです。お使いの冷蔵庫の年数や性能に応じて、買い替えか修理のどちらにするか見極めてみましょう。
なお、冷蔵庫の寿命の見極め方については、以下の記事でも詳しく解説しています。今お使いの冷蔵庫に不安のある方は、ぜひこちらもご参考にしてみて下さい。

-
冷蔵庫の寿命は何年?長持ちさせるコツと処分する方法を解説
- 冷蔵庫の寿命は、一般的には約10年で「消費動向調査 2025年3月 内閣府調べ」によると平均買い替え年数は13年。寿命のサインを見逃さず、早めに買い替えの判断ができるようにしましょう。またなるべく冷蔵庫を長持ちさせるには、使い方や設置環境を工夫することも大切です。この記事では、冷蔵庫の寿命が近づいているサインや長持ちさせるコツ、処分方法などを解説します。
- 詳しく見る
ジャパネット厳選のおすすめ冷蔵庫をご紹介!
まとめ:スペースごとの適正温度を知って鮮度長持ち&節電
冷蔵庫はスペースごとに設定温度が異なり、その温度にあった食材を入れることでおいしさや鮮度をより長持ちさせることができます。また、ドアの開ける回数を少なめにする、食材の詰め方を工夫する、熱いものは冷ましてから入れるなど、ちょっとしたコツに気をつけるだけで冷蔵庫の温度を安定させ、余計な電気代がかかることも防ぎやすくなります。
もし、長年使った冷蔵庫が冷えにくいときは、新しい冷蔵庫に買い替えることもおすすめです。どんな冷蔵庫にするか迷ったときは、今回おすすめしたジャパネットおすすめ商品もぜひご参考にしてみてください。